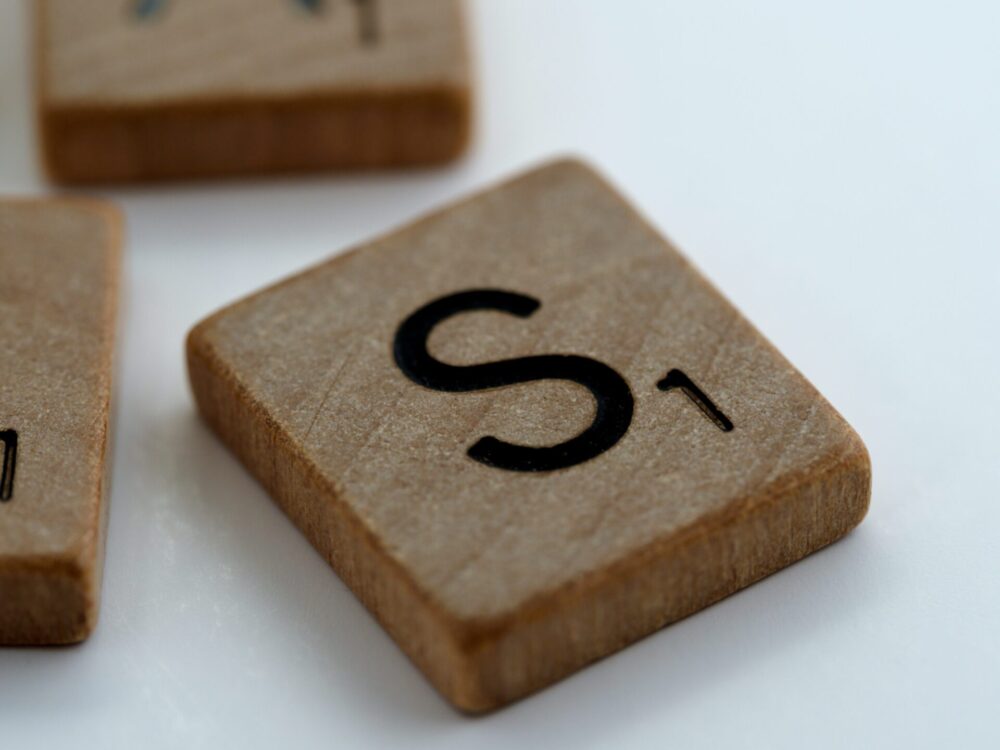「オニールの成長株発掘法を読んで」または「CANSLIMを知って」、もう少しCANSLIM「S」について詳しく知りたいと思われていると思います。
株式投資をしていると必ず出てくるのが「ウィリアム・オニール」ですね。
オニールの投資法である「CANSLIM」の
「S=Supply and Demand(株式の需要と供給)
~重要なポイントで株式の需要が高いこと~」
について、私なりに理解した内容をまとめるとともに、どのように投資へ活用しているのかについて触れていきたいと思います。
CANSLIM全体については、本サイト内のこちらの記事でまとめています。
続きを見る

CANSLIMを理解する3つの核心ポイントとスクリーニング法
参考
こちらの本を読んでポイントをまとめたものです。
まだ読んでいない方はぜひ一読されることをおススメします。
「オニールの成長株発掘法」
⇒ CANSLIMは「最も一貫した最高の成績を上げた手法の一つ」
目次
1. CANSLIMの「S」とは:株式の需要と供給に注目!
CANSLIMの「S」は、株式投資においても需要と供給の考え方が大切であり、どんなIQが高い人でもこの基本原理には逆らえないということが書かれています。
日常的な商品の価格もまた需要と供給によって決められますね。
レタスやトマト、卵や牛肉であっても販売されている価格は、その製品を入手できる量と、その製品を欲しがる人の数によって変わります。
企業が発行する株式数はそれぞれ異なっていて、多くの株式を発行している企業は供給が過多になりますね。
投資する銘柄の発行済み株式数を確認し、その銘柄の日々の出来高を確認すると需要と供給の実態をつかむことができます。
2. 発行済株式数から考える需要と供給
発行済み株式数が50億株もある銘柄と、5000万株の銘柄では仮に他の条件が全く同じであれば、5000万株の銘柄を購入した方が良い成績を期待できます。
発行済み株式数にも「浮動株」と「特定株」などがあり、これらの株式数によって「1株当たり」を考える基準が変わってきます。
本章ではこちらの内容について確認するとともに、需要と供給について確認していきます。
・発行済株式数の違いが与える影響
・発行済株式数が少ないと魅力が上がる理由
・「浮動株」の考え方も知っておく理由
2-1. 発行済株式数の違いが与える影響
発行済み株式数が違うと1株当たりのもつ影響度が変わりますので、発行済株式数が多くても・少なくてもどちらもメリットとデメリットがあります。
今回はオニールのCANSLIMを勉強していますので、需要と供給の観点から需要が高くて株価が動きやすい銘柄を探すことが大切なポイントになります。
50億株もある銘柄と、5000万株の銘柄について、仮に他の条件が全く同じという前提で需要と供給について確認していきたいと思いますが、かなり単純な内容となります。
発行済株式数が少ない方が株価の変動が柔軟で、少しの情報が大きな影響を与えます。
ポイント
50億株(発行済み株式数が多い)場合
・(供給)供給量が多く、なかなか株価が動かない
・(需要)大きく上昇させるにはかなり多くの買いの出来高が必要
ポイント
5000万株(発行済み株式数が少ない)場合
・(供給)比較的供給量が少なく、株価の変動が起きやすい
・(需要)ある程度の買いの出来高があれば上昇する
2-2. 少ない株式供給が魅力を高める理由
発行済株式数が少ない株は小型株・中型株が該当します。
逆に発行済株式数が多い株は大型株に該当します。
大型株の方が株価の動きが鈍くなる理由は、需要と供給だけではなく、その規模になると組織体制が古く、成長の速度も衰えるなど、大きくなりすぎて動きが鈍っているということになります。
一方で、大型株は一般的には下落しにくいこと、場合によってはリスクも少ないことが長所になることもあります。
近年はファンドが相当の資金力を持っているため、中小企業と同じくらいの速さで値上がりするケースもありますが、可能性を考えると中小型株への投資が重要と供給の面では有効です。
少ない株式供給となっている中・小型株は、大型株に無い柔軟な需要と供給のバランスがあります。
組織もまだまだ固まっておらず柔軟な判断が可能で、成長スピードが速い点も魅力です。
一方で、中・小型株は上昇スピードも速いですが、下落スピードも速いため、リスクが高くなるケースもあります。
CANSLIMのC・A・Nをクリアした銘柄から選定する前提であれば、少ない株式供給の方が上昇スピードが上がる可能性が高く魅力も高くなることがわかります。
2-3. 浮動株の考え方も知っておくと良い理由
発行済み株式数の中には「浮動株」「特定株」という考え方がありますね。
ここでは、マーケットのプロも注目するといわれる「浮動株」について知っておくべき理由をご紹介します。
浮動株は発行済み株式数から経営陣などが保有している安定保有株式数(特定株)を差し引いた市場に流通している株のことです。
つまり、浮動株が少ないということは、2-2でご紹介したとおり市場で流通している株が少ないということになり供給量が少なく、買いたい人が増えると株価が上昇しやすいということになります。
私が浮動株についてまとめた記事はこちらになります。
-

-
浮動株比率の調べ方を確認!2分で浮動株比率を調べる3つの方法
続きを見る
また、浮動株が少ないということは、安定保有株式数(特定株)が多くなりますのでこの場合のメリットについてみておきましょう。
特定株は経営陣が保有している株式等になりますので割合が大きい(大企業なら1~3%以上、中小企業ならそれ以上)場合には、経営陣のやる気がアップする可能性が高くなります。
具体的には、特定株が多いということは、経営陣が自ら自社の株をたくさん持っているということですので、株価が上昇すれば経営陣の資産が増えますので値動きは経営陣自らの利害に直結します。
よって、企業としての株価上昇に対する努力も期待できるため、良い買い候補になります。
私が特定株についてまとめた記事はこちらになります。
-

-
特定株とは売買される可能性が低い株!特定株を活用するの3つケース
続きを見る
3. 起業家精神のある経営陣は需要が高い
CANSLIMの「N」で大切だとされていた新製品や新サービスは起業家精神に富んだ経営陣を抱える、革新的でハングリー精神にあふれる比較的新しい中小企業から生み出される。とされています。
起業家精神があふれる企業と大手企業のような安定志向の企業では、需要と供給がどのように変わってくるのかについてまとめました。
3-1. 起業家と大企業の経営陣の差
起業家精神があふれている企業の経営陣は、さまざまなことにチャレンジしたり新製品・新サービスが生まれて企業成長が期待できる。という傾向があります。
一方で、大企業の多くは昔ながらの保守的な「管理人タイプの経営者」によって運営されていて革新的な決断やリスクのある行動をとったり、素早く行動して急速に移り変わる時代に追いつこうという意欲に欠ける。という傾向があります。
大企業の経営陣の課題を次のようにあげています。
大企業の経営陣が自社株を大量に保有しているということはない。これは重大な欠陥であり、大企業が正すべき努力課題である。こうした企業の経営陣および社員は自社の成功に個人的な関心を寄せていない。
優れた投資家の目にはそう映っても仕方がない。
オニールの成長株発掘法より
以上から、大企業の経営陣ではなく、中堅・中小企業などに近い起業家精神があって自社株を保有している経営陣の企業を選択することで、需要が供給を上回って株価が上昇する可能性が高くなります。
3-2. 革新的な企業が生まれやすい3つの業界
小規模な企業が急速に成長を遂げていくジャンルには傾向があります。
次の3つの業界からこのような企業が多くみられます。
ポイント
・サービス業
・ハイテク産業
・情報産業
上記はアメリカの業界ですが、日本では「サービス業」「情報通信業」「電気機器」「小売業」などのジャンルから急速に成長を遂げていく企業が生まれています。
3-3. 大企業が新製品を生み出した際の課題
大企業にも素晴らしい企業はありますし、経営陣が優秀であったり新製品が飛び出てくるところもあります。
ただし、株式投資をしていく上では、マンモス企業が重要な新製品を生み出すことがあったとしても、株価を著しく押し上げることにはつながらないことが課題となります。
巨大な企業にとって、その新製品が売上や収益に与える影響は軽微であり、例えると「大きなバケツに落ちた小さな一滴に過ぎない」とされています。
たしかに大企業の売上や利益を大きく変えてしまうような新製品が出ることは稀であり、それを期待するのであればもっと期待値の高いところに投資したいですよね。
4. 株式の需給バランスを見極めるポイント
株式投資では発行済株式数から需要と供給を考えていくことについてすでにご紹介しました。
実は、発行済株式数は常に一定ではなく、株式分割や自社株買いなどをおこなうことで市場で売買できる株数に変動が生じて需要と供給のバランスが変わることがあります。
株式分割をすることで流動性が上がりますが供給量が増える点が課題であり、自社株買いをおこなうことで流動性が下がりますが需要が増えるという点があります。
これはCANSLIMのC・A・Nを充足している銘柄が前提となります。
4-1. 過度の株式分割は供給量が増え重たくなる
企業は株式分割をおこなうことがあります。
例えば1株を1:2で分割する場合には、今持っている1株は分割後に2株として売買できるようになります。株価は分割のタイミングで半分になりますが、EPSも半分になりますね。
これを1:3や1:5でおこなわれると供給量が大幅に増えてしまうので、1:2や2:3で分割することが推奨されていますがそれであっても供給過多になりやすい状態になります。
過度な割合での分割や、過度な回数の分割を繰り返すと、企業が持っていたはずの本来の重要と供給のバランスが崩れてしまい、値動きの重い企業へと進んでいってしまいます。
株式分割を2回か3回おこなうと株価が天井を打つ傾向にあるようで、大きな株価上昇を見せる前年に前年に株式分割を行った企業は全体のわずか18%だったということですので、株式分割をした企業は候補から外していくのも大切な判断の一つですね。
4-2. 自社株買いはEPSが増え需要があがる
長時間かけて継続的に自社株を買っている企業というのは将来の株価の上昇見込みのある企業であり、自社株を10%保有していれば相当な量を保有している企業になりますので期待も上がります。
自社株を買うという行為は、流通する株式数を減らすだけでなく、企業が今後の売上や収益の改善を見込んでいることを暗示していることになります。
流通する株式数が減ると。企業の純利益は減った株式数分け合うことになりますのでEPSが上昇します。
CANSLIMの「C」「A」で大切だと言われていたEPSの増加率が増えるため、株価を押し上げで大化け銘柄になる可能性が出てきます。
成長企業だからこそ効果がある自社株買いで、収益が増加していない企業が自社株買いをしてもそれほど信頼性はありません。
5. 成長株でも負債比率が高い企業はハイリスク
ここまでの内容をふまえて、成長する銘柄かつ株式数の需要と供給のバランスが取れた銘柄が見つかっていれば、次にその企業の総資本のうち長期負債や社債が占める割合を確認しておくことが必要になります。
一般に、自己資本比率が高い銘柄、つまり負債の比率が低い銘柄ほど安全で優良な企業です。
金利が高くなったり深刻な不景気が訪れると、負債率が高い企業はEPSに大きな打撃を与えます。
また負債の多い企業はおおむね、低品質でハイリスクとみなされますが業種柄もあります。
革新的な企業が生まれやすい業界においては、負債率が高いとEPSが伸びずCANSLIMのC・Aの条件が崩れやすくなるリスクが高くなりますので、ハイリスク銘柄となります。
ただし、過去2~3年の間に、総資本に対する負債率が減少しているような企業は検討の余地があります。少なくとも利息の支払いが減るのでEPSが増加することにつながります。
もう一つ注意すべきは資本構成における転換社債の有無です。
社債が普通株に転換されると収益の希薄化につながりますので要注意ですね。
7. 最終的に需要と供給は出来高で判断する
ここまで需要と供給の話をいろいろな角度でしてきましたが、需要と供給を見極める最善策となると、日々の出来高を観察することになります。
出来高にはその銘柄の重要と供給のバランスが現れると言われています。
株価が一時的に下落するとき「出来高の減少が伴っていれば」、「大きな売り圧力がすべて出尽くした」「下落しても売りたい投資家が少ない(上昇すると思っている投資家が多い)」ことを示しています。
逆に、株価上昇時に出来高の大幅な増加を伴っていれば、一般投資家ではなく機関投資家による買いが入っていることを示しています。
下落した際に出来高が減少する「出来高売り枯れ」についてはこちら
-

-
出来高が減少して売り枯れになったらチャンス!買い時の見極め方とは
続きを見る
以上から、株価がもみ合いからブレイクするとき、出来高は少なくとも+40~50%以上になることが望ましいとされています。
一日で+100%を超えることも珍しくなく、これは大量の買いや株価のさらなる上昇の見込みが高いことを示しています。
これらは日足チャートや週足チャートで確認します。
上記のような出来高がさらに有効になるのは、株価のベース(ボックス)ができてそのベースを抜けて新高値を付けたときだと言われています。
「ベースを形成しているか毎週チャートを見る」
「正しいパターンが形成されたときに投資をする」
この2点をおこなうことで機関投資家による買い集めの状況下にあるかどうか、それともダマしなのかを見分けることができます。
まとめ
CANSLIMの「S」について自分なりに学んだことをアウトプットしてみましたが、「オニールの成長株発掘法」を読まれた際に感じたことは同じでしたでしょうか。
今回は、購入する銘柄の需要と供給について、現在の需要と供給だけではなく、このあと需要と供給がどう変わっていくのかについてもしっかり確認してから購入しようという内容でしたね。
CANSLIMの条件を満たす銘柄であれば、総資本の規模にか関わらず購入してよいが、総資本が少ない小型株の方が上昇時も下落時も値動きが激しくなります。
小型株を中心に選定しながら、さらに自社株をしている経営陣が多くの株式を保有している企業が投資対象として望ましいですので、こういった株を探しましょう。